社会的つながりがひらく発話の扉。小1女児の場面かんもく改善の秘密──ポリヴェーガル理論から見た場面緘黙の支援
目次
「話せない」から「話せる」へ──Fちゃんの変化を神経の視点から読み解く
場面かんもく症は、精神疾患(不安障害のカテゴリー)と定義されています(DSM‐5TR,2023)
2024年5月に【ミライ開花SMPT®】を受講した当時は幼稚園年長さんのFちゃんの事例を、自律神経の新たな視点から深堀してみたいと思います

Fちゃんは、小学校受験を5か月後に控えたタイミングで、「かんもく改善講座」を受講されました。
当初のFちゃんは、誰とも言葉を交わせず、表情も硬く、強い緊張を抱えている様子が見てとれました。しかし、それから1年、Fちゃんは大きく変化します。今では、学校生活を楽しみ、友達と外で大きな声で話すこともできるようになりました。
この変化を支えた背景には、「安心とつながり」を軸にした関わりがありました。そしてそれを理論的に支えてくれるのが、ステファンWポージェス博士が提唱するポリヴェーガル理論です。
家庭は本当に安全基地なのか、安心できる場所なのか
多くの保護者の方は、わが子の家以外で話せないな状態が長く続くことに不安を抱え、「なんとか話せるようにしなければ」と焦ってしまいがちです。その結果、知らず知らずのうちに子どもを追い詰めるような言動をしてしまうことも少なくありません。

しかし、そのような状態では、家庭は「安全基地」とは言えません。
子どもが心から安心し、自分を委ねることのできる場であるためには、まずは保護者自身が「安心」を届けられる存在である必要があります。
私が専門家として最初に行うことは、この家庭を「本当の安全基地」に整えることです。
Fちゃんのお母さまも、講座を通して関わり方を学び、ご自身の接し方を見直されました。
✅子どもの小さな変化や頑張りを見つけて言葉にし、
✅笑顔で応じ、
✅非言語の表現を大切にする。
✅スモールステップの発話チャレンジは、安心できる環境で子どもの自己決定を尊重しつつ計画的に進めていく
このような姿勢が積み重なって、
まず、お母さん自身が落ち着きを取り戻しました。
時々、Fちゃんはお外で話せないストレスが家庭で癇癪となってお母さんを困らせることもありましたが
お母さんは、落ち着いて適切な対応をとることによって、Fちゃんの癇癪はやがて治まりました。

家庭の空気が徐々に変わっていきました。
そうした変化によって、Fちゃんは「ここは安心できる関係だ」と神経レベルで感じられるようになり、少しずつ話せる人・場所が拡大していきました。
そして、受講から5か月後
小学校受験にも見事合格しました。
ポリヴェーガル理論とは?
ポリヴェーガル理論は、アメリカの神経科学者ステファン・W・ポージェス博士が提唱した理論です。この理論では、自律神経の働きが私たちの感情・行動・社会的なふるまいにどのように影響するかを説明します。
中でも特に重要なのは、「安心・つながり・社会的関係」を可能にする腹側迷走神経系(ventral vagal system)の働きです。
この神経系がうまく働いているとき、私たちはリラックスし、人と笑顔を交わし、声を出して話すことができるのです。
逆に、緊張や不安が強くなると、交感神経優位(戦う・逃げる)か、背側迷走神経優位(固まる・不動化・シャットダウン)の状態になり、話すことや他人との関わりが難しくなります。
場面緘黙の子どもたちは、まさにこの「安全ではない」と神経が判断している状態にあると考えられます。
安心の土台がFちゃんの神経をリラックスモードにした
Fちゃんの場合も、最初はまさに「凍りつき」のような状態でした。緊張が強く、身体もこわばり、声も表情も出せない。これは背側迷走神経が優位になっている、いわば「フリーズ」の状態です。
しかし、お母さまが関わり方を変え、
・小さなことでも「できた」と認める
・笑顔で接し、言葉が出ないことを責めない
・子どものペースを大切にする
という行動を積み重ねることで、Fちゃんの神経系が「安全だ」と感じられるようになっていきました。
これはポリヴェーガル理論でいう「社会的接近システム」の活性化であり、腹側迷走神経が働き始めたサインです。
その結果として、Fちゃんは少しずつ家庭以外でも、スモールステップのチャレンジを重ね、地域の中でお買い物をする時など、声が出せるようになりました。
一方、オンライン講座の受講中は、マイクの工夫などによりささやく声が、一緒に受講するメンバーに聞こえるようになりました。
Fちゃん自身も、「声が届いた」という成功体験を重ねていくことができました。受講中も笑顔いっぱいのFちゃんになりました。
受講生の子どもメンバーとママたち。終わりのご挨拶をしたところ。みんな笑顔です!

声と笑顔が引き出されたのは、神経の「安全」が整ったから
ポージェス博士は、「安全は治癒の前提条件である」と述べています。
Fちゃんにとって、言葉を出すことができるようになったのは、行動療法のアプローチによる“成功体験”の蓄積とともに、“神経系が安全を感じられるようになった結果”と言えます。
発話が可能になるには、脳の言語中枢の働きだけでなく、「自分は安全な場所にいる」という神経レベルでの感覚が必要不可欠です。
笑顔が増え、声が出るようになったFちゃんは、まさに神経が「つながっていい」「安心していい」と感じたことで、社会的関係の回路が十分に動き出した状態にあったのです。
学校・社会の中で安心が続くと、声も安定する
Fちゃんはこの春(2025年4月)、小学校に入学しました。そして入学後1か月が経ったゴールデンウィークに、友達家族とキャンプに行きました。そこでFちゃんは、「普通に大きな声で話していた」とお母さまが喜んで報告してくださいました。
これは、「安全でいられる社会的環境」が、家庭以外の場にも広がったことを意味しています。言い換えれば、Fちゃんの腹側迷走神経系が、さまざまな環境でも“社会的つながりモード”を保てるようになってきたということです。
このように、「安心の土台」がしっかりと築かれた子どもは、環境が変わっても自分の声でつながる力を発揮できるようになります。
まとめ:声を育てるのは「こころの安心基地」と「神経の安全」
Fちゃんの成長は、単に「話せるようになった」という変化にとどまりません。
それは、「神経が安全を感じ、人とつながれるようになった結果として、声が自然に出るようになった」という深い変化です。
ポリヴェーガル理論の視点を通して私たちが学べるのは、
✔ 子どもの“発話”だけではなく凍り付きがないか等の“状態”を理解すること
✔ 「話すこと」を目標にせず、「安心を得る関わり」を第一にすること
✔ 大人の笑顔や声かけが、子どもの神経系に直接働きかける力を持っていること
場面緘黙は「安全を感じられたときに自然とやわらいでいく、神経の反応」と考えられるかもしれません。
その子が持っている“話したい気持ち”を信じ、安心を積み重ねる支援を、これからも続けていきたいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
書籍紹介
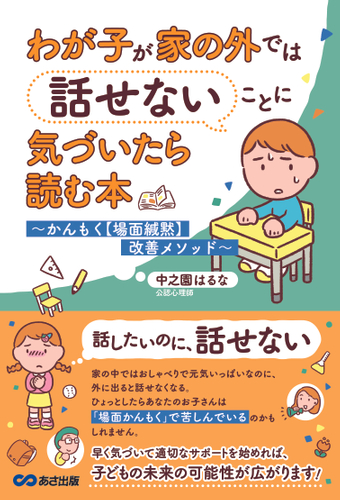
著者は、2013年に勤務する精神科クリニックにおいて、一人の場面緘黙症の男児と出会ってから独自の研究を重ね、かんもく改善講座【ミライ開花SMPT®】を開発し、実践してまいりました。これまで全国~海外までのクライアントさん延べ4000人をサポートしました。
約9割の場面緘黙症のお子様に改善がみられた【ミライ開花SMPT®】のハウツーを分かりやすく解説しています
年齢別10の改善事例を参考にしてみてください
*参考文献 ポリヴェーガル理論入門 心身に変革をおこす「安全」と「絆」

