新学期クラス替え。場面緘黙児が感じているプレッシャーと大人ができる寄り添い方を専門家が解説。
【子育てあるある】こんな時どうする?#話せなくて困っている #HSPお知らせピックアップ商業出版場面緘黙についておもうこと②
「励ましたつもりが、追い詰めてたかもしれない」
――クラス替えと、“学校で話せない子ども”の心に寄り添うために
新学期、クラス替え。期待と不安が入り混じる日
春4月、桜の花が満開に街を彩るころ――
新しい学年が始まるこの季節は、子どもたちにとって新しいスタートの時期です。

教室の掲示が張り替えられ、名簿が新しくなる日。
子どもにとって「進級・進学」「クラス替え」は、大きな転機です。
普通の子であれば、「どんな友達と一緒かな?」「新しい先生、優しいといいな~」など、ワクワク感が勝るかもしれません。
けれど、人とのかかわりに不安を感じやすい子や、言葉で自分を表現することにハードルがある子にとっては、この変化はとても大きなストレスになります。
先生はどんな人?
新しい環境でやっていけるかな?
私たち専門家が関わってきた中でも、この時期のタイミングで緘黙が悪化したり、再発するケースは少なくありません。
大人が想像する以上に、子どもたちの心は敏感に反応しています。
目次
「ちょっとは話せるようになるといいね」――その一言がプレッシャーに?

保護者の方からよく聞くのが、こんな声です。
「新しい友達、できるといいね!」
「ちょっとは話せるようになるといいね!」
励ましのつもりでかけた言葉。
でも、その言葉を聞いた子どもは、ほんの少しうなずくだけで表情がかたくなることもあります。
もしかしたら、胸の中は
「また話せなかったらどうしよう」
そんな思いでいっぱいだったのかもしれません。
その思いを、親にさえ言えない子もいます。
親が願う「前向きな一歩」も、子どもにとっては「できなかったらどうしよう」という不安の引き金になることがあります。
“話さない”のではなく、“話せない”ということ
家ではおしゃべりなのに、学校に行くと急に無口になる。
それが「場面緘黙(ばめんかんもく)」と呼ばれる症状です。多くは幼児期に発症し、1カ月以上続きます。
✅ 場面緘黙とは
場面緘黙(ばめんかんもく)とは、特定の場面や相手の前で話すことができなくなる状態を指します。家庭などの安心できる環境では普通に話せるにもかかわらず、学校や初対面の人の前など、緊張や不安を感じる場面では声が出なくなることが特徴です。
これは意図的に黙っているのではなく、強い不安や緊張から“話せない状態に陥る”反応です。
主に子どもに見られますが、早期に適切な理解と支援があれば、少しずつ改善が見込めます。
場面緘黙の子どもは、決してわがままでも反抗的でもありません。
頭の中では話したいことがあるのに、
話したいのに話せない
周囲にとっては「不思議」です
Q:場面緘黙って、どういう状態のこと❓
A:場面緘黙(ばめんかんもく)は、家庭では話せるのに、学校など特定の場面では1カ月以上にわたって声が出なくなる状態です。
一時的な恥ずかしさや緊張ではなく、精神疾患(不安症の一種)として、医学的にも診断される状態です。
子どもは「話したくない」のではなく、「話したいけど話せない」。
不安や緊張が高まり、声が出なくなってしまう心の反応です。
ただの恥ずかしがり屋ではありません。
甘えや性格のせいにせず、安心できる環境づくりと専門的な支援がとても大切です。
📌 詳しくは、医療機関や専門家にご相談ください。
時には体が固まってしまって動けなくなることもあります。
この状態は、不安や恐怖によって引き起こされる“反応”と言われています。
場面緘黙の原因は特定されておらず、複数の要因があるとされています。中でも有力な仮説は、「偏桃体の過敏性仮説」です。本人の意思でコントロールするのは難しいのです。
私たち専門家も、保護者の方にまず伝えたいのは、 「この子は“話さない”のではなく、“話せない”状態にある」という理解です。
クラス替えがもたらす“再スタートの負荷”
クラス替えは、場面緘黙の子どもにとって大きなハードルです。

-
仲良くなれた子が別のクラスに行ってしまう
-
担任の先生が変わり、信頼関係を築き直さなければならない
-
新しいクラスで自己紹介が求められる
こうした出来事は、ゼロからの再スタートを意味します。
一度少し話せるようになった子が、また話せなくなってしまう。
そのたびに「またダメだった」と自信を失い、ますます声が出しづらくなる。
しかも、周囲の子や先生が「どうしてしゃべらないの?」と口にしてしまうと、ますます萎縮してしまいます。
クラス替えのタイミングは、支援を受けているお子さんの状態を改めて丁寧に見直す大切な機会でもあります。
学校で話せない子に必要なのは「安心」と「居場所」

私たち専門家が繰り返し伝えているのは、 「話すこと」よりも先に、「安心できる環境づくり」が大切だということです。
-
話しかけるけれど、返事がなくても責めない
-
表情やしぐさでやりとりできたら、それを大切にする
-
書く・指さす・うなずくなどの“非言語コミュニケーション”を尊重する
-
話さなくても「ここにいてくれてうれしいよ」と伝える
話せないことよりも、その子が“そこにいる”ことを喜ぶまなざしが、少しずつ子どもの心をゆるめてくれます。
保護者だけで抱えず、担任や支援の専門家と連携しながら、 「この子らしい関わり方」を一緒に探っていきましょう。
親も、間違いながら育っている
保護者の方の中には、 「励ましたつもりが、追い詰めていたかもしれない」
と、自分を責めてしまう方もいます。

でも、
それに気づけたということは、
すでに大きな一歩です。
声かけを見直したその瞬間から、 お子さんとの関わりは変わりはじめています。
完璧じゃなくていい。
間違いながら、揺れながら、私たち大人も一緒に育っていくのです。
焦らなくていい。責めなくていい。

子どもは少しずつ変わります。
でも、その変化は「話すようになること」だけではありません。
-
表情がやわらいだ
-
学校に行ける日が増えた
-
自分で身支度や、学校の準備ができた
その一つひとつが、前に進んでいる証です。
子どもが学校で話せない――
その事実に気づいたとき、戸惑い、悩み、どうすればいいか分からなくなる。
そんな保護者の方に向けて、著者自身が支援現場での経験と実践的なメソッドをまとめた一冊があります。
📘『わが子が家の外では話せないことに気づいたら読む本』
公認心理師として精神科クリニックで多くの緘黙児と向き合ってきた中で、
どの家庭にも共通する「最初の不安」と「小さな前進」がありました。

この本は、保護者様が場面緘黙のわが子と向き合う日々の中で
「どう関わればいいのか」「何を大切にすればいいのか」を、具体的に、わかりやすく伝えるためのものです。
📖おかげ様で発売から半年で✨重版出来✨
学校では話さない――
「性格の問題?」「いつか自然に話すようになる?」
そう思いながら、戸惑いや焦りを抱えている保護者の方へ。
📘 『わが子が家の外では話せないことに気づいたら読む本』 は、
公認心理師として精神科クリニックで数多くの場面緘黙児と関わってきた著者が、
支援の現場で実際に用いてきた改善のステップや、親の関わり方を、わかりやすく紹介する実践書です。
✔ どう声をかけていいのか分からない
✔ 学校とどんな連携をすればいいのか不安
✔ 「このままで大丈夫なの?」と自分を責めてしまう
そんなママの思いにひとつひとつ寄り添いながら、
焦らず・責めず・その子のペースに寄り添う具体的な方法をお届けします。
『わが子が家の外では話せないことに気づいたら読む本』
おかげ様で発売半年で重版出来となりました!
必要な人に届きますように
この一冊が、あなたとお子さんの未来を変える第一歩になるはずです。
📢 お客様の声
学校で話せないわが子を見て、ずっと「どうして?」と焦っていました。
この本を読んで、「話さないんじゃなくて、話せなかったんだ」と分かったとき、涙が出ました。
我が子に対して、無理に話させようとして責めたり、焦ったりしていた自分に気づき、反省しました。
でもこの本にあった声かけの例を参考にしたら、子どもが表情で返してくれるようになって…。
少しずつでも関係が変わっていくのを感じています。
読みながら、「うちだけじゃないんだ」とホッとしました。
実際の事例がたくさん載っていて、「こんなふうに対応していいんだ」と分かることが本当に多かったです。
今では、担任の先生とのやりとりにも前向きにお願いすることが出来ています。
🗣️ 「親のNG行動にハッとしました」
本を読んで、親のNG行動ばかりしていました。
よかれと思ってしていた声かけや接し方が、実は子どもを追い詰めていたかもしれない…と気づき、胸が痛くなりました。
でもこの本には、どうやって切り替えていけばいいかも書かれていて、救われました。
読後は、自分の気持ちにも少し余裕が持てるようになりました。
🔍 このブログに含まれる主なキーワード
-
学校で話せない子ども
-
場面緘黙とは
-
クラス替え 不安
-
新学期 子ども 話さない
-
話せない子 どう対応
-
親の関わり方
-
子ども 緘黙症
お問い合わせはこちら
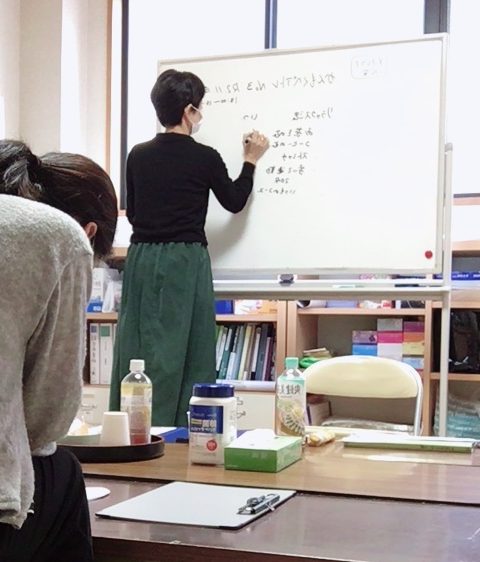
近年、多様化する価値観のなかで、心の問題も多様化、複雑化しています。うつ、社交不安などに加えて発達障害、ゲーム依存、コミュニケーションについての相談が増えています。精神科クリニックにも在籍し子どもから大人まで、カウンセリング延べ2,000人。クライアントの悩みに寄り添い、適切な心理療法を用いて問題解決へ向けてサポートします。




