学校では話せない場面かんもく児。その先にある“不登校”というサイン-親が知っておきたい7つの視点
「場面かんもく、そのうち治ると思っていました。しかし徐々に悪化している気がします」
これは、私の所に相談に来られた保護者様からよく聞く話です

公認心理師の中之園はるなです。
2013年から場面かんもく児と保護者様の支援をしています。2024年9月に、これまでの支援の経験をまとめた本を(株)あさ出版様から出版させていただきました【わが子が家の外では話せないことに気づいたら読む本】
今日のテーマは、以前から保護者様のお悩みとしてよく聞く、場面かんもく児と不登校の事についてまとめてみました。
ちなみに不登校の「定義」は以下です
目次
📘 文部科学省における「不登校」の定義
1. 欠席日数の基準(年間30日以上)
文科省の調査では、不登校児童生徒とは「病気や経済的理由ではなく、心理的・情緒的・身体的・社会的要因で登校しない(登校したくてもできない)状態が、
年度間に30日以上続いている児童生徒」を指します
-
「病気や経済的理由」が欠席の原因であるケースは対象外。
-
欠席が連続または断続して30日以上の場合が含まれます 。
2. 背景となる要因
単なる欠席日数ではなく、「学校に行けない/行きたくても行けない」という心理的・情緒的・身体的・社会的な原因が伴っていることが要件となります
学校や社会との関係にストレスを抱えるなど、さまざまな背景が影響していることが前提です。
3. 「不登校」に含まれるケース
具体例としては、友人・教員との関係、生徒自身の無気力、不安などを理由に登校できない状況が含まれます
一方、病気や経済的理由(例えば家庭の経済的事情)、または新型コロナウイルス感染回避などによる欠席は対象外です
4. 高校生でも同様の基準
高校生についても同様で、病気や経済的理由以外で**30日以上欠席しているケースが「不登校」**として扱われます
1. 「話せない」から「行けない」へ──場面緘黙と不登校の関係性

場面緘黙(ばめんかんもく)とは、家庭など安心できる場所では話せるのに、学校や外の環境では声が出せなくなる状態を指します。これは「恥ずかしがり屋」や「性格の問題」ではなく、れっきとした精神疾患(不安症のひとつ)であり、子ども自身の意志ではどうにもならない症状です。(DSM5-TR)
この“話せない”状態が続くことで、やがて学校生活そのものが苦痛になり、不登校に至るケースがあります。子どもにとっては、「学校=苦しい場所」「話すことを求められる場所」になり、登校すること自体が大きな負担になるのです。
場面かんもく症が直接の原因で不登校になるわけではありません。話せないことはあるけれど、楽しく学校に行くことが出来ている子もいます
しかし、学校環境によっては、場面緘黙と不登校は、決して別々のものではなく、相互に影響し合う関係にあるということを、まずは大人が正しく理解する必要があります。
2. なぜ場面緘黙の子は不登校になりやすいのか

場面緘黙の子どもたちが不登校になりやすい理由は、大きく分けて以下の4点です。
-
他者からの誤解や偏見
話せないことを「無視された」「挨拶しない」と受け取られ、孤立しやすくなります。 -
自信の欠如と無力感
話せないために参加できない、評価されない体験が続き、自己肯定感が下がっていきます。 -
強い緊張と過覚醒状態
学校では常に神経を張りつめており、放課後にはどっと疲れが出る…そんな生活が続き、身体的・心理的に限界を迎えます。 -
自己否定の連鎖
「自分なんてダメだ」「どうせできない」といった考えが根付き、他者や社会とのつながりを避けるようになります。
これらの要素が絡み合うことで、「話せない」が「行けない」につながってしまうのです。
3. 不登校になった時、親がまず知っておくべきこと

お子さんが不登校になったとき、
親としては「どうして?」「このままで大丈夫?」と、不安と焦りでいっぱいになると思います。しかし、焦って「何とかして早く学校に戻さなきゃ」と行動すると、逆効果になることがあります。
不登校になってしまったわが子に対して、親御さんが陥りやすいNG行動は以下の3つです
- 学校には行くべきという親の価値観だけで説教する
- 行かないのは心が弱いから「頑張れるだけ頑張ろう」と励ます
- 子どもが悩みを話しているのにまともに聴かない「そんなの気にすることないよ」と軽く考える
このような態度でこともと向き合ったとき、何が起こるのでしょうか?

子どもは、親には“自分の辛さは理解してもらえない”と寂しい思いをするでしょう。
そして、学校に行けないことを“また責められる”と感じ、心を閉ざしてしまうかもしれません。
その後は、親に本心を言えなくなり、本音を吐き出す場所がなくなり、ますます追い詰められてしまうのです
もし、このような親子関係であったとすれば
家庭が、安心安全な場所と言えるでしょうか?
ここで大切なのは、「なぜ登校できないのか」を正しく理解すること。
場面緘黙が背景にある場合、子どもは「行きたくない」のではなく、「行くことがつらくて仕方がない」状態にあるのです。
その苦しさは、想像以上に深く、言葉にできないほどのものです。まずは、子どもの内側で何が起きているのかに目を向けてあげてください。
4. 親が取るべき態度──焦らず、責めず、安心をつくる

お子さんが不登校になったとき、親ができる対応は次の3つです。
① 責めない・評価しない
「なぜ行けないの?」「また休むの?」といった言葉は、子どもにとっては“否定”や“攻撃”として受け取られます。
まずは「大丈夫だよ」「疲れたんだね」と、そのままの存在を受け止める言葉を届けてください。
② 安心の基地としての家庭を整える
学校で緊張を強いられていた子どもにとって、家庭は数少ない“素”の自分でいられる場所です。
だからこそ、安心できる空気、責められない空気を家庭の中に整えることが、回復の土台になります。
③ 行動の中に“元気のサイン”を探す
言葉ではなく、表情や遊び、食欲、好きなことへの集中など、行動の変化に注目することで、子どもの内側にあるエネルギーや変化を見つけることができます。

5. 回復の第一歩は「話すこと」ではなく「安心して存在できること」
場面緘黙や不登校への支援は、「話せるようにする」「学校に戻す」ことがゴールではありません。
まず大切なのは、「自分はここにいてもいい」と思える安全な場所があること。
それが、子どもが“自分の力”を取り戻していく第一歩になります。
私たちが目指すのは、子どもが「話せる子」になることではなく、「自分らしく生きていける子」になること。
安心 → 自己表現 → 自己決定という段階をふむ支援が、将来の自立につながっていくのです。
6. 家庭を基盤に、“第二の居場所”を見つけていく
家庭が安全基地であることはとても大切です。けれども、そこに“とどまりすぎる”ことで、親子が「閉じた世界」に入ってしまうリスクもあります。
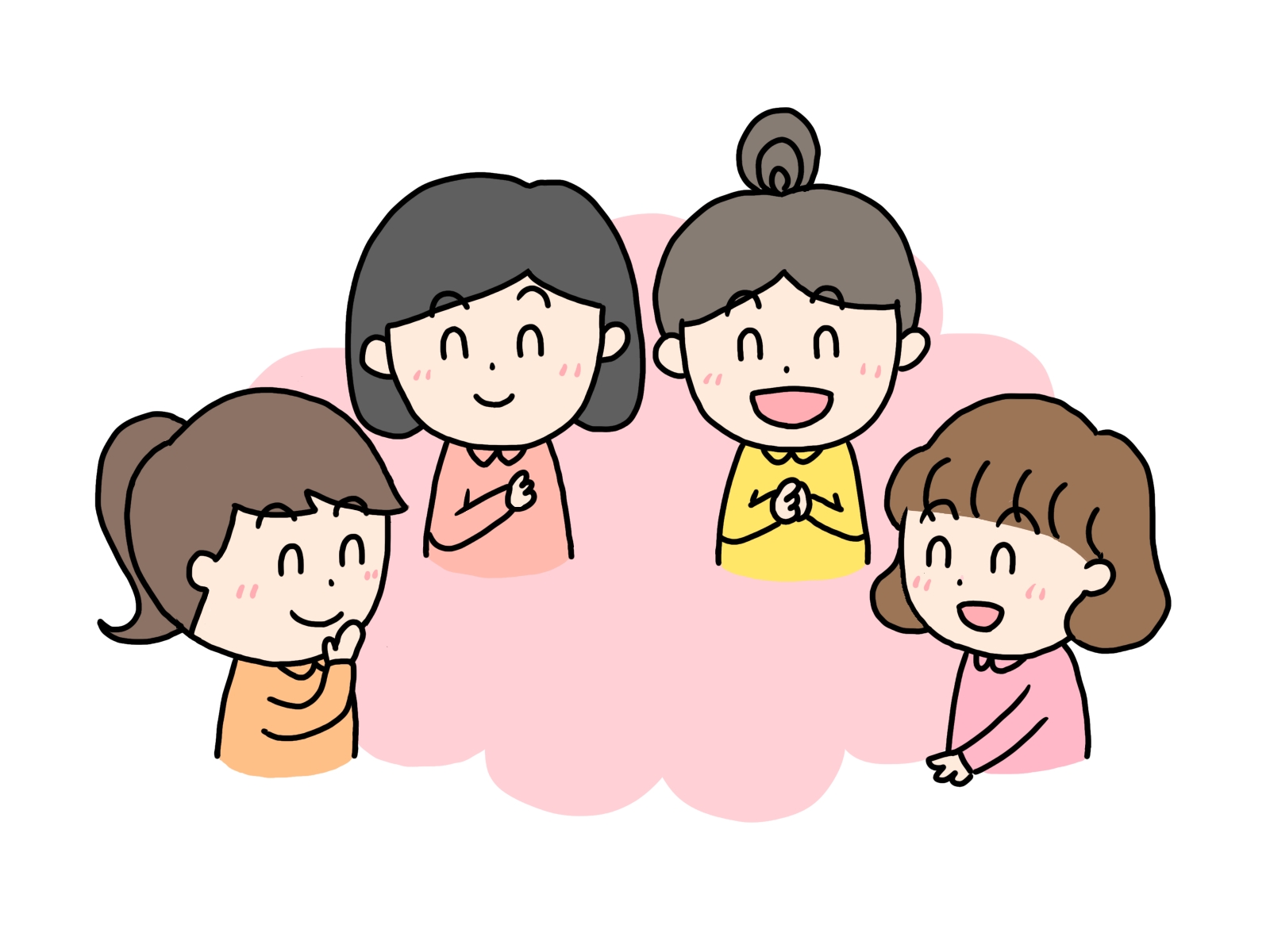
ときに、親も子も、お互いに依存的になり、「このままでいい」と殻にこもってしまうことがあるのです。
そこで意識したいのが、“第二の居場所”の存在です。
-
放課後等デイサービスや支援施設
-
習い事やスポーツ教室
-
図書館やフリースペース
-
オンラインでの趣味コミュニティ
-
信頼できる第三者のいる環境(親戚、近所、地域)
最初は見学だけでも構いません。「行ってみたいな」と思える場所、「いても大丈夫だ」と思える空間を、子どもと一緒に探していく姿勢が大切です。
“学校に行く”ことが目的ではなく、“社会とどうつながるか”を一緒に考えていきましょう。
7. 小さな一歩を一緒に喜ぶ──そして親ができること
とはいえ、不登校が長引くと親御さんも「このままでいいのだろうか」と不安になることと思います

学校に行けないことが長期化すると
家でも暗い顔が増えた。
家での会話が減ってきたという事も起こるかもしれません
そんな時は、子どもと一緒に遊んでください
楽しむことを忘れないでくださいね
不登校なのに「遊ぶ」なんて!と思いますか?
いいえ、楽しむことは「悪」ではありません
むしろ、リラックスして自律神経が整います。
楽しむコツは、子どもの好きな事に親の方から近づいて行く
子どもの世界を楽しむことです

実際に私のクライアント様で、お父さんが、中学2年の不登校の息子さんに対して上記の実践をされたら、不登校が解消したという事例があります
それまで、親子で一緒に楽しむことがなかったそうです。
息子さんの好きな事、関心があることを使ってコミュニケーションを取った結果、子どもの意思で学校に戻ることが出来たのです
(わが子が家の外では話せないことに気づいたら読む本 P182)。
➡子どもが、今日少し笑った。
➡好きなゲームを一緒にやって夢中になっていた。
➡それまで、家族とも話さなくなっていたのに、小さく「うん」と頷いてくれた。
それはすべて、立派な回復のサインです。
親だからこそ、その小さな変化を見つけ、一緒に喜んであげられるのです。
私たち大人は、「何かをさせる」ことに注目しがちですが、
子どもが“動けるようになる”のは、「自分で動きたくなったとき」。
そのためには、
わが家が安心感と信頼関係に見ていた場所であることが必要です
そしてある程度の時間が必要です。
親は、子どもにとって最も大きな支援者であり、導き手になれる存在です。
だからこそ、「この子を信じて、待てる力」こそが、支援の最前線にあるのです。
8. 最後に──必要なときに、つながってください
私はこれまで、場面緘黙に悩むご家族4,000人以上と関わってきました(不登校児含む)。
その経験をもとに書き下ろした書籍がこちらです
📘 『わが子が家の外では話せないことに気づいたら読む本』(2024年)
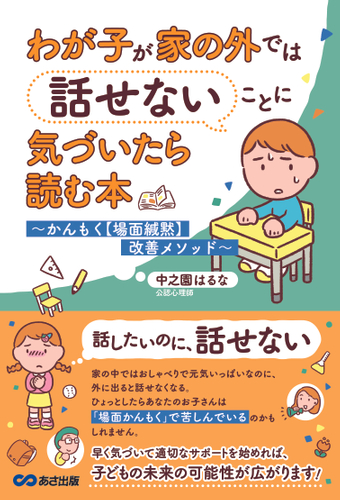
- 場面緘黙の基礎知識
- 家庭でできる具体的な対応、
- 支援の進め方までを、豊富な実例とともに解説しています。
また、より個別の状況に合わせたサポートをご希望の方には、オンライン個別相談(初回カウンセリング)もご用意しております。
「今の我が子に合う支援を知りたい」「誰かに整理してもらいたい」そんなときは、どうぞ気軽にご連絡ください。
➡ 書籍のお求めはこちらからhttp://www.asa21.com/smp/book/b650078.html
➡【初回30分個別相談】お申込みは公式LINEから受け賜っております。
こちらから自動で申込リンクが配信されます↓↓
https://s.lmes.jp/landing-qr/2003789191-J0b9322Z?uLand=QcIP0j
話せるようになる日は、ゴールではありません。
自分で考え、感じ、選び取って生きていける力を育むこと。それが、支援の本当の目的です。
そのために、今日も一歩ずつ。
親子で進んでいきましょう。私たちは、いつでもその歩みに寄り添います。



