5歳のかんもく児・小さな一歩がつなぐ未来「話せた!」の背景にある親子の関わりとは?
こんにちは
中之園はるなです

2025年も後半戦、7月に入りました!それにしても暑いですね~
熱中症にならないように、水分補修はしっかりしてくださいね。
さて
先日は、20歳過ぎても変化があるよ!という卒業生のママにインタビューさせていただいた内容の一部をご紹介しました。
今日は現役受講生さんの登場です。
25年4月生【Fさん】の受講3ヵ月目に起こったかんもくの娘さん事例をご紹介いたします
変化の出発点:まずは気持ちを知ることから
Fさんの娘さんは、5歳(年中さん)です。幼稚園ではなかなか声が出せず、お友達や先生と話すことが難しい状況でした。そんな中、ママは親が最初の支援者であると聞き、自分に改善のサポートが出来ればと考えて【ミライ開花SMPT®】講座の基本コースを受講中です。毎回のホームワークに取り組む際、「今、子どもはどんな気持ちなんだろう?」「どれくらい不安なのかな?」という視点で、お子さんの気持ちにしっかりと向き合われました。今、座学の2ヶ月が終わって、いよいよスモールステップ【家庭編】の実践が始まりました。

娘さん(Sちゃん)に伝えたことは
チャレンジシートを取り組む前に、話せないのはなぜかということを話したところ、「練習したら、Sちゃんが小さくてできなかったことも、大きくなってできるようになるってこと?」と自分なりに解釈した言葉で返してくれました。
また、前回取り組んだ不安レベルの表を見ながら、今お家の中で練習していけるところはどこかなと一緒に考え、レベル2とレベル4の行動目標を立てました。
実施する際のシートは、簡素化したものにし、リビングの見えるところに貼り、できたらスタンプを押すようにしました。
そして、スタンプが20個たまったらグミを買おうと約束しました。
ここで重要なのは、いきなり”親の感覚”あるいは“親のこうあって欲しい期待”でチャレンジ目標を決めるのではなく
わが子の不安の程度を「見極めている」ことです。
「どんな場面なら安心できる?」「どんな相手なら話せそう?」という対話を重ねることで、
お子さんの中にある小さな“できそう”を見つけ出していきました。
目次
合意形成:未来を一緒に描く

不安のレベルを共有したあと、ママはSちゃんにこう伝えました。「練習すれば、話せるようになるんだよ。今すぐじゃなくていい。少しずつでいいんだよ。」
この声かけは、お子さんにとって安心を与えると同時に、「未来への可能性」を見せるものでした。するとお子さんは、「それって少しずつでも練習すれば、お友達と話せるの?」と、前向きな反応を見せてくれたのです。
この瞬間、親子で「じゃあ、やってみようか」という合意形成ができました。このステップが、後の大きな変化の土台となります。
第一歩:家の中でのチャレンジ
話す練習は、まず「一番安心できる場所」(家庭)からです。
ママと一緒に考えたのが、「インターフォンに出る」ことです
レベル2のチャレンジ目標を立てた時点で、インターフォンがなった時、どんな言葉を言うか、玄関に一人で行くか、玄関開けたら挨拶をして、荷物をもらったらお礼を言うということを一緒に確認。
そして、宅配日時を設定した日にもインターフォンがなったらどうするか行動確認をしていたため、インターフォンがなると「出る!はい!だよね?」と反応し、その後も自信をもって「こんにちは。ありがとうございました。」と荷物を受け取ることができました。
一人で行くことはなかったため、できた後は「はい!って出て、こんにちは、って言って、荷物もらったら、ありがとうございました。って言えたよ~」っと喜んでいました。
凄い凄い。ママと一緒じゃなくてもぜ~んぶSちゃん一人でできたねっ」と褒めてあげました。夫にも週末に自分でも伝えており、「もうひとりでできるよ。」と得意げに話していました。
Fさん、凄いですね~しっかりと具体的な計画を立てています。
お子さんは見事にそのチャレンジを成功させました。
「できた!」という喜びが伝わってくるエピソードですね。この成功体験が、次のステップへの大きな自信につながります。
そして次のチャレンジでは、
Sちゃんのレベルとしては少し高めのレベル4でしたが、お子さんが「やってみたい」というのでチャレンジしました。これは、受け身から能動的への大きな変化。
話すという行為が「怖いこと」から「楽しいこと」に少しずつ変わっていく、大切なプロセスです。
レベル4の伯母との電話では、1回目ビデオ電話で話し、恥ずかしそうにしながら、答えるときは私を見ながらではあるものの、「違うよ。そうだよ。」などの返事をしたり、途中画面から隠れたりしながら、「今からテニス行くの。」と話すこともできました。
ここで私自身がビデオ電話ではなく普通の電話が良かったのかと不安になったのですが、先生から助言もいただき、娘にビデオ電話で話してみるか、声だけの電話にするか相談し、ビデオ電話にすることにしました。2回目のビデオ電話では、中2日であったこともあったためか、「おはよう。」と自分から挨拶したり、「パパはまだ寝てるのよ」などと自分からも会話し始める様子も見られました。
3回目の電話は、私自身の用事で電話したのですが、娘も「話したい!」と参加し、私の姉が質問してくれたことにも、ちゃんとビデオを見ながら返事をしたり、「今SちゃんはK(塾)をしてるの」とカメラを操作して宿題を見せたり、「従姉はなにしてるの?」などと自分からも質問してました。
4回目の電話では、今日のご飯は?とご飯の質問に答え、その後「Mちゃん(伯母のこと)ちのご飯はなぁに?」と質問された内容を、聞き返すこともしていました。
幼稚園での思いがけない出来事:練習の成果が花開く
そしてまだ地域編のチャレンジもしていない段階ですが、なんと、家庭編でのその努力が幼稚園でも実を結ぶ日がやってきました。
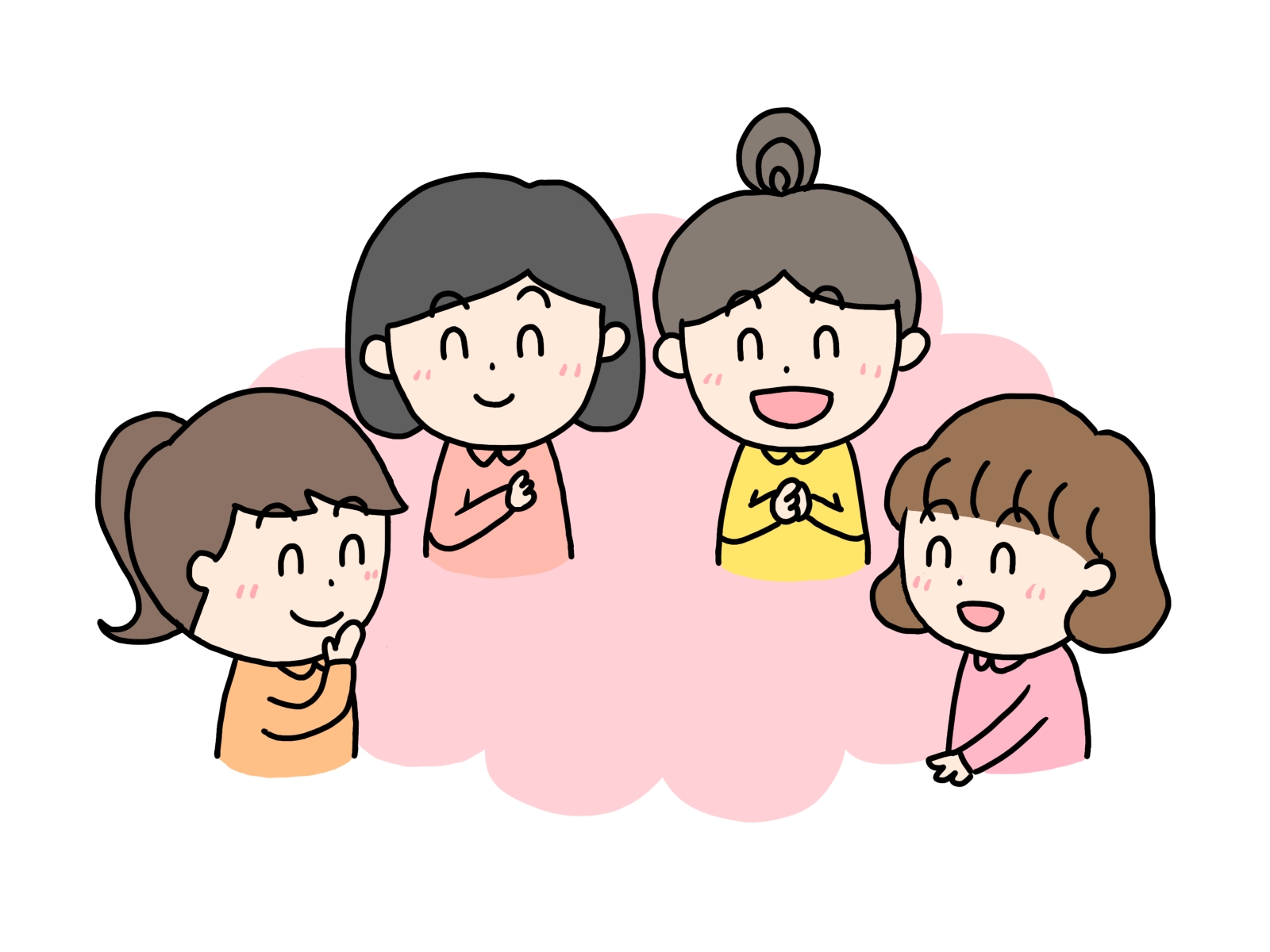
その出来事とは?
このチャレンジをする過程で、娘の中で自信が付いたり不安が軽減していたのかもしれません。
家庭編の1週目の金曜日に幼稚園で仲のいいお友達に「はい。って言ってみて」と言われたときに、耳元で「はい」って言えたんだっ」とささやき声ができたと教えてくれました。
そして、次の週の月曜日には、年長から仲良くなったお友達にも「はい」って言えたこと。
火曜日には、初めてはいと言えたお友達に、耳元より少し離れたところで、ちょっとだけ声量が大きくなった「はい」が言えたり、「プリキュア」って言えたよ。と教えてくれました。
担任の先生も、娘が耳元に手を添えている姿を見られていたようで、娘が話せていることを私と一緒に喜んでくださいました。
素晴らしいですね!
ある日、お友達が「『はい』ってお返事してみて」と言ってきた、これはよくあることなんです。いつもだったら、こんなこと言われると緊張して話せないものですが・・・
そのとき、Sちゃんは、家庭での成功体験から勇気を得ていたに違いありません。ママからの報告でお判りですね。
✅Sちゃんは、誰かに促されなくても「自らお話ししてみたい」気持ちが湧いてきていましね。
✅だから、小さな声でお友達の耳元で「はい」と答えることができました。
お友達もきっとうれしかったのでしょう、会話がはずみます。「好きなキャラクターを教えて」と続けました。お子さんは再び耳元で、そのキャラクターを答えることができたのです。このやりとりは、単なる会話の成功ではなく、家庭での成功体験が土台となり、お友達との信頼関係と安心感の中で行われた大きな一歩でした。
なぜこの変化が起きたのか:専門的な視点から
このような変化の背景には、いくつかの重要な要素があります。
① 不安の見える化と調整
場面緘黙のお子さんは、「話したい気持ち」と「話すことへの不安」がいつもせめぎ合っています。今回のケースでは、まず親御さんが【ミライ開花SMPT®】講座で習った通りに、不安を丁寧に見える化し、子ども自身が「自分の不安」に気づき、言葉にできるようサポートしたことが大きなポイントです。
② 合意形成による安心感
「一緒にやってみよう」と親子で合意を形成できたことで、お子さんの中に「これは自分で選んだチャレンジ」という感覚が生まれました。この「自己決定感」があることで、取り組みに対する主体性と前向きさが格段に上がります。
③ 小さな成功体験の積み重ね
「できた」という経験は、自己効力感(=自分にはできるという感覚)を高めます。電話でのやりとりという小さな成功が、お子さんにとっては「次もやってみたい」という気持ちを引き出す大きなきっかけとなりました。
④ 受け身から能動への移行
初めは受け身だったコミュニケーションが、次第に自発的・能動的になっていくプロセスは、安心と信頼の中でしか育まれません。ママの姉(伯母さん)との電話のやりとりでその感覚が育ち、「お話するって楽しい」「もっと話したい」気持ちが沸き上がって行動につながったのです。
おわりに:親子で歩む“話す力”の育ち
たった一言のお返事、一つの質問。それがどれほど大きな意味を持つか—このお話はそれを教えてくれます。

お子さんの「話したい気持ち」を信じて、焦らず、丁寧に、段階を追ってサポートしたごママの姿。そして、小さなチャレンジをひとつずつ乗り越えながら、勇気を得て未来を描けるようになったお子さんの力。
「話すこと」は、心と心をつなぐ手段です。不安のと緊張が強い場面かんもく児にその力を育てるために必要なのは、
- まずは、「無理をさせないこと」
- 「信じて待つこと」
- 「一緒に歩むこと」。
- この3つの柱が、今回の変化を支えた最大の要因でした。
これからも、お子さんのペースを大切にしながら、「できた!」の経験を積み重ねていってほしいと心から願っています。
※注意点:この事例は一例です
今回ご紹介したケースは、家庭でのチャレンジから一気に幼稚園(最も不安が強い場所)へと自然につながり、成果が見られた非常に良い例ですが、すべてのお子さんに当てはまるわけではありません。
通常は、「家庭編 → 地域編 → 学校編」という段階を丁寧に踏むことが推奨されます。
良い事を訊いたと思っても、マネしないでください
いきなり幼稚園や学校でのチャレンジを試みると、お子さんにとっては大きな負担となり、かえって不安や混乱を招いてしまうこともあります。焦らず、段階を飛ばさずに進むことが大切です。
なぜなら、わが子の状態を見極めずに、他のお子さんの成功例をそのまま真似してしまうと、支援が逆効果になってしまう(自己流は“事故る”)リスクがあります。
まずは「わが子のデータ」をとること。今どんな気持ちなのか、何ができて、何が難しいのかを丁寧に把握することが、適切な支援への第一歩です。
そのうえで、小さなステップを一つずつ確実に積み上げていくことが、安心できる成長につながります。どうかその子に合ったペースで、あたたかく支えながら、一緒に歩んでいきましょう。
*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~
今日も最後までお読みくださりありがとうございました。
【お知らせ】
東京開催!かんもく親子フェス 2025年8月23日(土)14時~16時半
場所:渋谷区立長谷戸教育館 音楽室(小)
ホームページhttps://g.co/kgs/45QfKyi
会場定員:30名
オンライン定員;100名
【体験発表】をしてくれるのは24年5月生(卒業生)です。5歳年長女児の素晴らしい変化をママが体験発表してくれます。他にも何人か予定しています。
子どもに「お話が楽しい」と思える未来をプレゼントしませんか?それが出来るのはパパママです。
皆様のご参加をお待ちしています
お申込みは➡こちらから
*~~*~~*~~*~~*~~*~~





