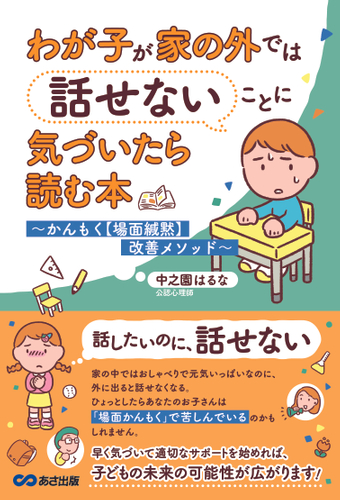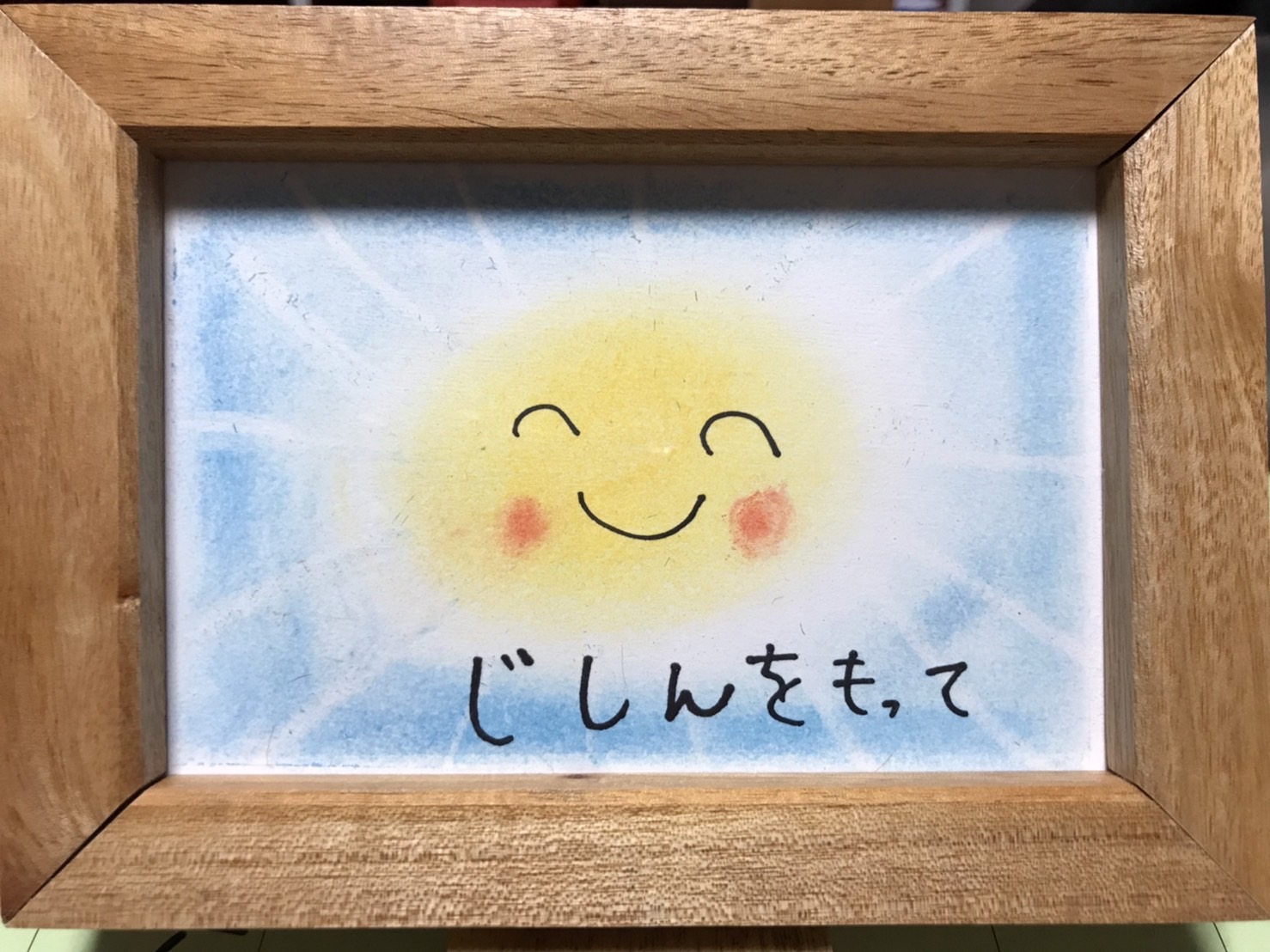小4・ASD併存場面かんもく児が8ヶ月で変化したわけ。プレイセラピー7年しても「変化ゼロ」だったのに
こんにちは。中之園はるなです

かんもく改善メソッド【ミライ開花SMPT】を「受講して本当に良かった」
そう語ってくださったお母さまは、小学4年生の娘さんと7年間、病院のプレイセラピーに通い続けても変化が見られず、不登校などの困りごとも増える一方——という現実に向き合ってこられました。
本記事では“なぜ変わらなかったのか”、そして“なぜ8ヶ月で前に進めたのか”を、専門家の視点で読み解きます。キーワードは条件づくりと段階づくり、そして親の関わりの再設計です。
Before:挑戦そのものを避ける日々
お母さまはこう振り返ります。
「娘が『話すのなんて無理だよ』と言うので、その意思を尊重してきました。Zoomの講座も『絶対に出ない』と…。」
「病院からのアドバイスは『寄り添ってください』。でも困りごとは増えるばかりで、親子の不安は大きくなる一方でした。」
以前の親子の会話はこうでした
母「無理なら、やめておこうか」
娘「……うん」
“優しさ”から始まった回避の許可は、結果的に挑戦の機会そのものを減らすことにつながってしまいました。
目次
なぜ「寄り添うだけ」では変化が起きにくいのか、専門家視点で読み解きます
1)回避が強化される学習サイクル
不安場面を避けると一時的にホッとします。この“安心”が回避行動を強化し、次の挑戦がますます難しくなる——行動分析でいう負の強化が働きます。
「やめておこう」は、短期の平穏を与える一方、長期の前進を遠ざけます。

2)“人・場所・活動”に依存する発話
場面かんもくは、人・場所・活動という文脈で発話が大きく左右されます。
プレイセラピーのように安全な個室での自由遊びは、家庭内の安心には似ていますが、学校やオンライン集団など目標場面への架け橋が弱いと、一般化が進みません。
3)目標が「気持ちの支え」に留まり、行動の設計が不十分
「寄り添い」は必要条件ですが、“何を・どの順で・どの条件ならできるか”の行動設計が欠けると、前進の指標が曖昧になり、振り返りも難しくなります。
4)親の関わりが“救済者”に固定
わが子が困りそうな前兆で先回りし、代弁・回避を許可し続けると、子の自己効力感が育ちにくくなります。親の優しさが、意図せず回避ループの支えになってしまうのです。
*自己効力感とは
やればできる自分であるという自覚
人の役に立つことが出来る自分であるという自覚
を指します
チャレンジして、成功し、他者からの賞賛と感謝される体験が乏しいと「自己効力感」は育ちにくくなります。